別注 リム皿
割れにくい、木のプレート
お椀を別注として作っていただく中で、ふと「お椀だけでなく、長く使える木のお皿があったらどうか?」と思い、ろくろ舎の酒井さんに相談したのが始まり。とっても素敵な1枚を作っていただきました。
使いやすいサイズ・デザインに拘って作っていただいたリム皿は、汎用性が高いのが特徴。カレー・パスタ・ハンバーグなどのメイン料理にぴったりですし、ビーフシチューやリゾットなども食べやすいようになだらかな傾斜がついていて、リムがあることで掬ったときにテーブルを汚してしまうことも防げます。朝食のパンとスクランブルエッグ、ソーセージを入れてワンプレートにしたり、食べ過ぎた日の翌日のサラダプレートにもおすすめ。すべすべとした木肌や漆が美しく、ありそうでなかった漆のお皿になりました。
リム皿を選ぶ
落としても割れにくく、木の暖かみを感じられるプレートはもともと人気ですが、安価なものは軽くてプラスチックの塗装がすぐ剥げて黒く変色してしまったり、拭き上げが甘くてカビてしまうこともあり、ある程度の時期で買い換える"使い捨て"というイメージもありました。このオンリー椀のリム皿は程よく重さがあり、使っているうちにお皿がずれていくこともありませんし、漆の持つ抗菌作用のおかげでカビも生えにくいです。サッと拭くだけですぐに乾いてくれるので、陶器に比べて乾きやすいなとも思います。
そして、木のお皿が持つ "割れない安心感" も見逃せないポイント。陶器のお皿は、洗うときに割れないように無意識に気を使いますが、木のお皿はそこまで気にしなくていいので本当に気持ちが楽です。忙しい時や、家事を急いで済ませなければいけない時の食事にはついついこういった木のお皿に手が伸びますね。プラスチックではなく、小さい頃から本物に触れさせたいけれど陶器のお皿だと怪我が心配な小さな子どもの食器にも良いですよ。尖ったカトラリーよりも、木製のものを使う方が傷がつきにくくておすすめです。
木地にはケヤキを使用し、その上から漆を塗る漆椀。漆とはウルシの木に傷を入れて出てくる樹液のことで、使い込むほどに味が出るのが魅力です。自然の素材だからこそ、人と同じようにそれぞれ個性があり、全く同じものは存在しません。そのため、同じ工程を行うにしても、ものによって手間のかかり方が異なるのですが、高い完成度に差はなく、こだわって大切に作られているのに変わりありません。
拭き漆は、木目が見えることにより、ぬくもりのある印象が持てます。木によって目の表情が異なるので、1つしかないお椀という特別感もより感じやすいのではないでしょうか。
・拭き漆 生漆:漆の原料をお椀に塗って拭きとるという作業を繰り返しながら仕上げます。
・拭き漆 黒漆:漆の原料に鉄分と熱を加えながら攪拌させることで、黒く化学変化させたものを使用します。生漆と同じく、何度もお椀に塗って拭きとるという作業を繰り返して仕上げます。
モノの価値を再定義する
丸物木地師である酒井義夫さんが福井県鯖江市で立ち上げた木製品の工房、ろくろ舎(ロクロシャ)。北海道生まれの酒井さんは、木製品メーカーへの入社を機に福井県鯖江市へ移住します。そこで木地師であり伝統工芸師でもある山口怜示さんに師事、木地師としての技術を習得しました。退社後には、越前漆器の伝統工芸師である清水正義さんの元で技術を磨き、2014年に木地製作の工房ろくろ舎(ロクロシャ)を立ち上げました。伝統的な丸物木地師としての技術を継承しながら、木材を中心に素材・製法にこだわることなくプロダクトを製作する、「価値の再定義」をコンセプトにしています。
| サイズ | 直径約23.3×高さ4cm |
| 重量 | 約232g |
| 素材 | ケヤキ、漆 |
| 箱有無 | 有 |
対応機器
-
電子レンジ:×
食器洗浄機:×
オーブン:×
使い始めに
- ◇塗り上がったばかりの漆器には独特の匂いがあります。気になる場合は、日の当たらない風通しの良い場所で保管してください、自然と匂いがなくなります。
注意事項
-
◇電子レンジ、食器洗浄機、蒸し器には使用しないでください。
◇たわしなどのご使用は避け、スポンジの柔らかい面と中性洗剤でお手入れしてください。
◇色あせの原因となりますので、直射日光や紫外線は避けて保管してください。
◇一点一点手作業でお作りしていますので、完全に同じものがない点についてご了承くださいませ。また、入荷時期によっては細かな仕様がカタログと異なる場合がございます。
修理について
- ◇漆の塗り直しや修理も対応しております。カスタマーサポートまでご相談くださいませ。
ブランド紹介
ろくろ舎(ロクロシャ)
丸物木地師である酒井義夫さんが福井県鯖江市で立ち上げた木製品の工房、ろくろ舎(ロクロシャ)。木地師とはろくろやノコギリ、かんなを用いてお椀や重箱、盆等の木工品を加工・製造する職人さんのことを言います。北海道生まれの酒井さんは、木製品メーカーへの入社を機に福井県鯖江市へ移住します。そこで木地師であり伝統工芸師でもある山口怜示さんに師事、木地師としての技術を習得しました。退社後には、越前漆器の伝統工芸師である清水正義さんの元で技術を磨き、2014年に木地製作の工房ろくろ舎(ロクロシャ)を立ち上げました。伝統的な丸物木地師としての技術を継承しながら、木材を中心に素材・製法にこだわることなくプロダクトを製作する、「価値の再定義」をコンセプトにしています。
| 商品 | 価格(税込) | 在庫 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|

|
¥16,500(税込) |
△
残り1点 |
カートに追加されました
別注 リム皿には、他にもこんな仲間がいます
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
別注 卵椀¥11,000(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
【受発注】オンリー椀 ヒョウタン¥9,900〜(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
【受発注】 オンリー椀 キホン¥11,000〜(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
【受発注】 オンリー椀 ハゾリ¥11,000〜(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
【受発注】オンリー椀 ドンブリ¥16,500〜(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
別注 ナベワン¥12,100(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
BASE01 汁椀¥6,600〜(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
BASE01 飯椀¥6,600〜(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
蕎麦鉢¥16,500(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
酒器セット 1¥8,800(税込)
-
ろくろ舎(ロクロシャ)
酒器セット 2¥11,000(税込)





















.jpg)



















































.jpg)



.jpg)



.jpg)






































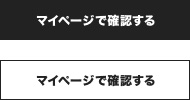












.jpg)







